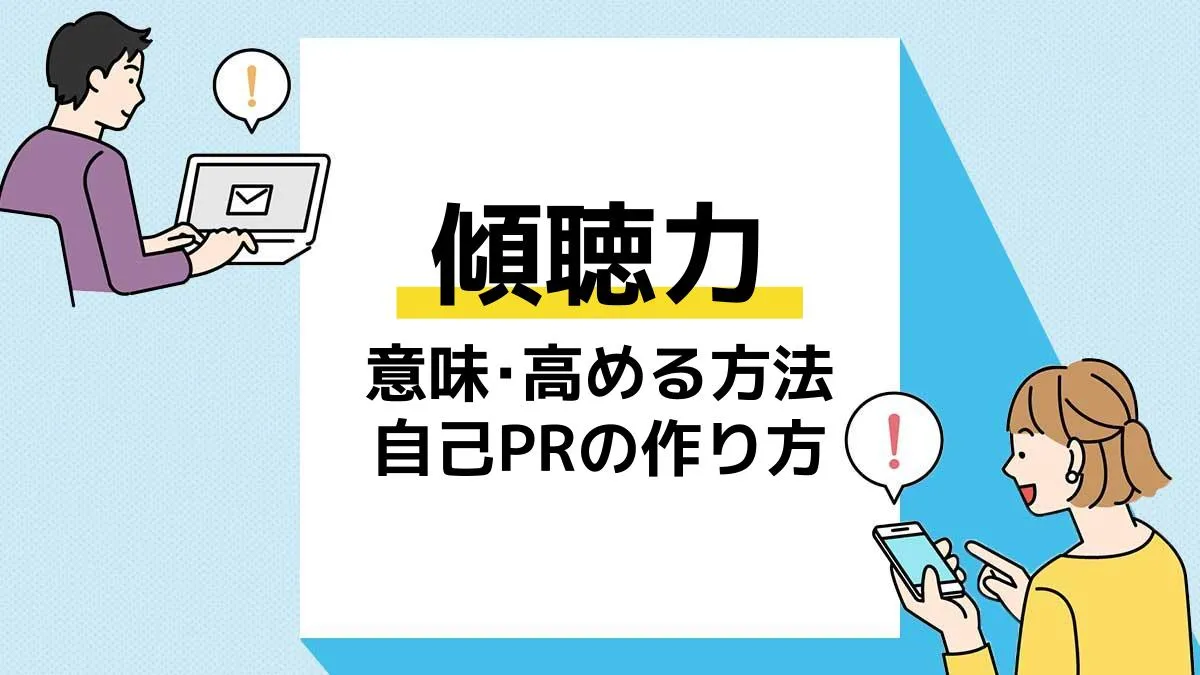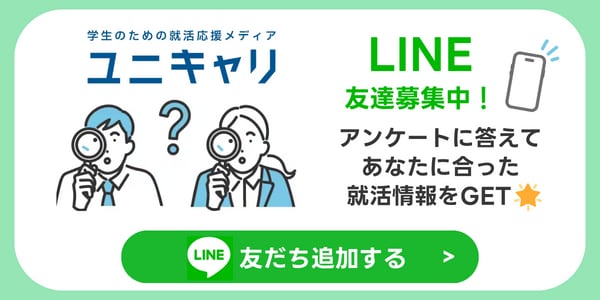傾聴力(けいちょうりょく)とは、相手の話を聞く力です。ただ話を聞くだけではなく、話す様子から潜在的な感情を読み取ったり、相手の話をより深く聞き出したりするスキルを指します。
傾聴力を高めることは、信頼関係を築くことにもつながります。日常的な会話であっても、傾聴力を高めることを意識してコミュニケーションをとってみましょう。
この記事でわかること
- 話を「聞く」と「聴く」には明確な違いがある
- 3種類の「傾聴」を段階的に身につけることで、傾聴力が高められる
- 日々のコミュニケーションでトレーニングをすれば、傾聴力が高い人になれる
目次[表示]
傾聴力とは:相手が話す内容や様子を深く理解して聞き取る能力
傾聴力とは、「相手の話を聞く力」です。相手が話す内容や様子から感情や悩みを理解できる人を、傾聴力がある人といいます。
傾聴力は、他人の意見や感情を尊重するためのスキルのひとつであり、コミュニケーションや人間関係の構築に役立ちます。
言葉の意味を理解するだけではなく、表情や声のトーン、姿勢なども見ながら話を聞くことで、相手が潜在的に感じていること・話したいことを引き出せるでしょう。そして、相手の話を適切に要約したり問題解決に導いたりできる力も含めて「傾聴力」といいます。
「聞く」「聴く」「訊く」の違い
「きく」には次の3種類の漢字が存在します。
| 漢字 | 意味 |
|---|---|
| 聞く | ・音や声を聞くこと ・特に何も意識をしなくても耳に入り、 ・受動的に耳に入ること ・「聴く」「訊く」の意味としても 使われることがある |
| 聴く | ・人の話に集中して耳を傾けること ・「聞く」よりもさらに一歩踏み込んでいる |
| 訊く | ・質問をすること ・「なぜそうしたのですか?」など 疑問形の場合に使われる |
傾聴力の場合、「聴く」「訊く」の意味合いが強くなるでしょう。
3種類の「傾聴」の意味
「傾聴」には次の3つの種類があるといわれています。
それぞれの傾聴の意味を理解し意識することで、傾聴力を高められるでしょう。
受動的傾聴
受動的傾聴とは、相手の話をありのまま受け入れて聞くことです。
「ありのまま受け入れること」であり、相手が話している途中で割り込む・否定する・急かすことはせず、最後まで話を聞くことがポイントです。
相手が話しやすい雰囲気や環境をつくることも、傾聴において重要になるでしょう。
反映的傾聴
反映的傾聴とは、繰り返すように反応しながら相手の話を聞くことです。
話を繰り返すというのは、相手が「◯◯でした」と言った際に、「△△ということですかね」といったように自分なりの言葉で言い換えて伝えるイメージです。似た言葉、同じ言葉を使いながらリアクションをすることで、相手は「理解をしてもらえている」という感情になります。
言葉だけではなく、感情や表情といった言葉以外でも似たリアクションをすることもポイントです。

あくまでも違和感がないよう、自然に行うようにしましょう。
積極的傾聴
積極的傾聴とは、相手の話にしっかりと耳を傾けている意志を伝え、話を引き出すように聞くことです。
相手の話を要約する、自分の感情を言語化することで、相手はさらに深い話をしやすくなるでしょう。その結果相手の本音を引き出したり、より深い思考力を促したりできます。
また、お互いの理解が深まり、信頼関係の構築にもつなげられます。
傾聴力を高めるメリット
傾聴力を高めることには、次のようなメリットがあります。

傾聴力の高さは、仕事だけではなくプライベートでも役に立ちます!
相手や会話の内容に対する理解が深まる
相手の話を聞くことができれば、話の本質・相手の本音を理解しやすくなります。
表面上の言葉だけではなく、言葉にはしていない潜在的なことも理解できるようになれば、より深い部分にある悩みに寄り添えるようになるでしょう。
理解が深まるほど相手に役立つアドバイスができるため、悩みや問題解決につながりやすくなるはずです。
信頼関係を構築しやすくなる
傾聴力を高めることができれば、相手からの理解・信頼を得られ、結果的に信頼関係の構築につながります。
家族や友人、恋人、先輩と後輩、部下と上司など、社会人にはさまざまな人間関係が存在します。ときには、他人には言えないこと、センシティブな話をすることもあるでしょう。
こういったとき、相手の話に耳を傾け悩みを引き出し、寄り添いながら的確なアドバイスができれば、これまで以上に深い関係を築けるはずです。
話の聞き方・伝え方で、相手は「大切にしてくれている」「蔑ろにされている」と感じるため、傾聴力の高さは重要だといえるでしょう。
自分自身の理解も深まる
相手の話に耳を傾けることにより、自分自身の理解も深まっていくでしょう。
相手の話をなんとなくで捉えるよりも、本質を理解したほうが気持ちに寄り添うことができます。理解が深まれば、疑問が浮かんで質問をしたり、相手が求めているリアクションができたりするはずです。
そういった行動により、相手は「自分の話を聴いてくれている」と感じるため、さらに踏み込んだ話もしてくれるでしょう。
傾聴力を高めるトレーニング方法
傾聴力を高めたい方は、日々の会話で次のことを意識してみてください。
傾聴力は少しずつ高められるものです。これらのコツを常に意識しながら、コミュニケーションのなかで実践してみてください。
相手の話を聞く姿勢・態度を意識する
まずは、相手の話を聞くときの、自分の姿勢や態度を意識してみましょう。
- 仕事をしながら聞く
- スマートフォンを操作しながら聞く
- 体や目線を相手に向けずに聞く
このような状態は真剣に話を聴いているとはいえず、相手も話す気持ちが失われてしまいます。
傾聴力を高める具体的なテクニックを実践する前に、話を聞く姿勢や態度ができているかを確認してみてください。
相手の話を聞く割合を増やす
話をする割合として、相手と自分、7:3を目安にしてみてください。
会話をするとき、「自分から話しかけないといけない」と思う方もいるかもしれません。しかし、相手の話に耳を傾けたいときは、相手の話を聞き出すことを重視し、自分が話す割合が少なくなるよう意識してみましょう。
相手の反応を見ながら発言する
自分がどう思っているか、どう伝えるかも大切ですが、相手が話を理解しているか、納得しているかも重要です。
理解・納得しているかを知るためには、相手の表情や話し方を見ればある程度わかるでしょう。
例えばアドバイスをしたとき、口では「わかりました」と言っているのにもかかわらず、相手の表情がどこか暗かったり、あまり反応がよくなかったりすることがあるかもしれません。こういったときは、アドバイスに納得できていない、話が難しく理解し切れていない可能性があります。
「わかりました」と言った相手の言葉を受け入れるのではなく、「ほかにも不安がありますか」「実践できそうですか」と質問してみましょう。また、その場でシミュレーションを行い、理解できているかを確認してみるのもおすすめです。
相手のペースに合わせて会話する
話す人や会話の内容により、ペースや呼吸のリズムはさまざまです。ペースやテンポ、トーン、リズムを相手に合わせることで、「寄り添っている」という意志を伝えやすくなります。

相手に合わせることを「ペーシング」といいます。
慣れ親しんだ友人であれば、ペースを合わせることは難しくないかもしれません。しかし、仕事だけで関わる相手、初対面の相手では簡単にはできないでしょう。そういったときは、無理にペースを合わせにいくよりも、相づちなど難しくないことから合わせてみてください。
相手の話に肯定する
話を聞くときは、相手の話を肯定することも大切です。基本的には相手に寄り添いながらコミュニケーションをとりましょう。
自分の価値観とは異なることを言われたとき、無意識に「いや」や「でも」といった否定をする方がいるかもしれません。傾聴力では相手を理解しようとする姿勢や、話を引き出すことが重要です。すぐに否定をしてしまうと、相手はより深い話をやめてしまうこともあるでしょう。
もし相手と異なる意見をもっていた場合でも、まずは「うんうん」「なるほど」などと相づちをします。そして、「なぜそう思ったのか」などを聞いたあと、「自分はこう思う」「でも相手は◯◯だと思っているかもしれない」など、直接的な否定はせず自分の意見を伝えてみてください。
そうすることで、相手は「他人は自分とは違う考えをもっているんだ」「もしかしたら自分が間違っていたかもしれない」と考えることができるはずです。

最後まで聞かないまま否定をすると、相手は嫌な気持ちになったり言い合いになったりする可能性があります。気持ちのよいコミュニケーションをするためにも、まずは相手の話を最後まで聞くように意識しましょう。
傾聴力が高い人の特徴
傾聴力が高い人の特徴は、次のとおりです。
身近に傾聴力が高いと思う人がいるときは、その人の真似をしてみましょう。話しているときの心地よさや、話したくなるような相づちは参考になるはずです。
相手の話を遮らない
どんな内容であっても、途中で話を遮らない人は傾聴力が高いといえるでしょう。
話が白熱すると、話の途中でも「いや」や「でも」といった否定の言葉を入れたり、自分の話に切り替えたりする方もいます。
傾聴力が高い人は相手から相談されたとき、アドバイスばかりをするのではなく、「自分自身はどうしたいのか」などを聞き出してくれるでしょう。自分の意見を言うよりも、相手の話を聞き出そうとする人は傾聴力が高いといえます。
相手にとって心地のよい相づちをする
心地のよい相づちをしてくれると、「この人は自分の話を聴こうとしている」「理解してくれようとしている」と無意識のうちに感じるでしょう。そうすることで、今まで伝えていなかった本音や、潜在的に感じていた深い話もしやすくなります。
相づちはただすればよいというものではありません。過剰な相づちは、反対に「話を聴いていない」と感じさせ、反応が薄いと「理解をしていない・興味がない」と感じさせるため、相手にとって心地よい程度が重要です。
「この人と話していると、つい話しすぎてしまう」と感じるときは、相手が心地よい相づちをしてくれており、その人は傾聴力が高いといえるでしょう。
相手がしてほしい質問をする
相づちに加え、相手がしてほしい質問をするのも傾聴力が高い人の特徴です。
してほしい質問ができるということは、相手の話を十分に理解している証拠です。質問によって、相手が伝え切れていなかった部分まで聞き出せるため、話の理解はさらに深まります。
ただ何かの質問をすればよいのではなく、話の状況を整理する質問や、相手の心情をより深く知るための質問をしてみましょう。

会話はどんどん進むので、質問をその都度考えるよりも、自分自身が話を理解するために浮かんだ質問をするのがいいですね。
就活・ビジネスシーンでは特に「傾聴力」が役に立つ!
傾聴力は仕事、プライベートどちらのシーンでも必要なスキルです。
ビジネスシーンであれば、社内はもちろん顧客や取引先といった社外の人とのコミュニケーションでも役立ちます。円滑なコミュニケーションは信頼関係の構築につながり、結果的に自分の成績や企業全体の利益にもつながっていくでしょう。

学生時代からはもちろん、社会人になってからも傾聴力を磨いていきましょう!
傾聴力のある人が必要とされる理由
傾聴力はさまざまな企業で注目されるスキルのひとつであり、自己PRや長所としてアピールできます。具体的な理由は、次のとおりです。
社内メンバーやクライアントと良好な関係を築けるため
傾聴力があると、相手が伝えたいことを正確に理解したうえで適切な対応ができるため、コミュニケーションに関するミスの軽減ができます。
正しいコミュニケーションがとれるスキルを身につけていれば、同僚や上司、顧客などとよい人間関係を構築でき、仕事の結果にもつながるでしょう。
相手のニーズを理解できるため
傾聴力があれば、同僚や顧客の声から正しいニーズを把握できます。
特に営業や接客といった顧客とのコミュニケーションが重要になる仕事では、相手がどんなことで悩んでいるのか、潜在的に何を求めているのかを知るため傾聴力が必要です。
日々の問題解決に役立つため
業務では日々さまざまな問題解決に取り組みます。
傾聴力がある人は相手の立場になり、さまざまな角度から問題にアプローチできます。そのスキルは個人が抱える問題だけではなく、チームの問題解決能力の向上にもつながるでしょう。
さらに、自分の意見と他人のアイデアを組み合わせ、新しい解決策を生み出すことも期待できます。
自己PRで傾聴力をアピールする場合のポイント
自己PRで傾聴力をアピールするときは、次のポイントを考えてみましょう。
- 企業がどんな能力を求めているのかを確認する
- 傾聴力を発揮したエピソードを伝える
- 第三者からのフィードバックや評価を引用する
- 傾聴力が応募先企業でどう活かせるかを説明する
- 傾聴力をほかの言葉に言い換えできないかを検討する
企業がどんな能力を求めているのかを確認する
自己PRを考える際、まずは応募する企業の文化や価値観を確認しましょう。その内容を踏まえ、企業が求める傾聴力のタイプを把握します。
傾聴力がある人を求めている場合でも「時間をかけて積極的に意見を出し合える」「スピーディに仕事を進められる」といったように、求められる傾聴力の種類が違うかもしれません。
志望する職種で黙々と作業する業務が多い場合、傾聴力よりも「論理的思考力」や「自己マネジメント力」をアピールするほうが有効になる可能性があります。
-
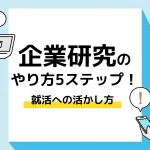
-
企業研究のやり方5ステップ!ノート・シートの作成方法や就活への活かし方を解説
就活における企業研究は、企業の詳細な情報を収集し分析するプロセスです。この記事では、企業研究のやり方を5ステップで解説します。情報収集の方法や企業研究で得た情報を就活で活かすポイントなども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
続きを見る
傾聴力を発揮したエピソードを伝える
自己PRに限らず、ES(エントリーシート)や面接でアピールするときは、具体的なエピソードを伝えるのがおすすめです。学校でのゼミ・研究の活動やボランティア、アルバイト、サークルなどのなかで、傾聴力を発揮した経験がないか振り返ってみましょう。
「自分には傾聴力がある。◯◯の仕事に活かせる」ではアピールとしては物足りないため、どんなシーンで傾聴力を発揮できるか、傾聴力のスキルは業務のどこで活かせるかを伝えます。
例えば、「傾聴力の高さにより、研究活動で立ち塞がった問題を解決に導いた」「アルバイトでお客様の潜在的な声を把握してニーズを掴み、売上につなげた」などです。

具体的な自己PRの例は「傾聴力をアピールする自己PRの例文」で紹介しています。
-
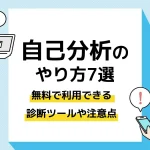
-
自己分析のやり方7選|簡単にできる診断ツールや注意点を解説【就活】
自己分析とは、過去を振り返って自分を理解し言語化することです。この記事では、自己分析の方法7選や注意点、行き詰まったときの対処法などを解説します。無料で利用できる自己分析ツール5選も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
続きを見る
第三者からのフィードバックや評価を引用する
学校の先生や教授、先輩や後輩、友人、家族などに「自分に傾聴力を感じたことはあるか」を聞き、その答えを引用するのもおすすめです。主観的に「自分は傾聴力がある」と伝えるよりも、周りがどう感じたか、どう評価してくれているかという客観的な意見含めると、説得力がアップします。
例えば、「グループ研究のなかで、教授から『リーダーとして全員の意見をよく聞き、みんなが納得できる結論が出せるよう貢献していた』と評価されました」などと、自分に対する評価を引用する方法です。

傾聴力以外にも、自分にはどんな長所や特徴があるのかを聞いてみると、ESや面接でアピールできることが増えそうですね!
傾聴力が応募先企業でどう活かせるかを説明する
自己PRの方向性は、「業務のなかでどう活かせるか」「スキルや自分の存在がどう貢献できるのか」につながる内容にしてみましょう。
例えば、「自分の傾聴力は、お客様に寄り添い、同じ目線で物事を考えることができる」などです。寄り添うことができれば、顧客が抱える悩みの解決ができ、結果的に企業の利益にもつながるはずです。
傾聴力をほかの言葉に言い換えできないかを検討する
「傾聴力」という言葉は、類語に置き換えることもできます。「傾聴力」を自分の特徴に近い言葉に言い換えることができれば、長所をアピールしやすくなる可能性があります。
| 傾聴力の言い換え | 詳細 |
|---|---|
| 調和力 | 異なる要素や人々との 調和を保つ能力 |
| 理解力 | 他人の意見やアイデアを受け入れ、 考慮する能力 |
| 洞察力 | 他人や状況を理解し、その背後の 要因や動機を把握する能力 |
| 問題解決力 | 問題を分析し解決策を考え 実行する力 |

傾聴力の高さをアピールする学生は、ほかにもいる可能性があります。そのため、「傾聴力」を自分の個性や強みに近い言葉に言い換えることで、より具体的なアピールがしやすくなるはずです。
-
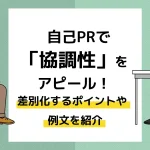
-
自己PRで「協調性」をアピール!差別化するポイントや例文を紹介
自己PRで協調性をアピールする際には、過去の経験から「協調性を発揮したエピソード」を伝えることが重要です。この記事では、自己PRで協調性をアピールするポイントや注意点、エピソードを交えた例文などを紹介します。
続きを見る
自己PRで傾聴力をアピールする場合の注意点
自己PRで傾聴力を伝えるときは、次のポイントに注意しましょう。
伝え方次第では、注意点を解決して自分のアピールポイントにすることができます。
「傾聴力がある=聞き上手」ではない
傾聴力とは、相手の話を聞くことだけではなく、相手の考えを尊重し適切に対応するスキルのことです。受け答えが上手な「聞き上手」とは異なるため、それを踏まえたうえでアピールしてみましょう。
「多くの人の悩みを聞いた」「聞き役に徹することが多い」というのは、聞き上手に寄せたアピールです。傾聴力の高さを伝えたいときは、相手の話を聞くなかで何を意識したのか、どんな問題を解決してきたのかを考えてみてください。
自主性や積極性がない人だと認識されないようにする
相手の話を聞くことを中心にアピールすると、「自分の意見を言わない人」という認識になることも考えられます。
実際の業務では、相手の声に耳を傾けるだけではなく、自分の意見を主張するシーンもたくさん出てきます。そういった場で「自分の意見を積極的に言えない人」「周囲に流されやすい人」と思われないよう、自主性もアピールすることを意識してみてください。
相手の話を聞きながら自分の意見も伝え納得してもらったことなど、問題解決に導いた具体的なエピソードを盛り込むと、傾聴力の高さがアピールしやすくなります。
志望する企業・業務に関連しないアピールは避ける
傾聴力に関するエピソードが、志望する企業や業務内容にマッチしていないと、アピールが不十分になる可能性があります。
例えば、子どもと関わる業務を志望している場合、「高齢者との関わりのなかで寄り添えた・傾聴力を身につけられた」といったエピソードではターゲットが異なるため、採用担当者はイメージを掴みにくいかもしれません。
子どもと関わる業務に向けた志望動機や自己PRであれば、子どもと関わるなかで身についたスキル、コミュニケーション術などをエピソードに挙げるほうがアピールにつなげやすいでしょう。

「傾聴力」が志望する企業・業務に関連しない場合、ほかのスキルをアピールしても問題ありません。
傾聴力をアピールする自己PRの例文
ここでは、学生生活のなかにある5つのできごとから、「傾聴力」をテーマにした自己PRの例文を紹介します。
学校での活動
学校での活動の例
私の強みは、相手の考え方や価値観を受け入れる傾聴力です。
大学の授業では、異なるバックグラウンドや知識をもつメンバーと共同で研究を進める機会がありました。各メンバーがもつ独自のアイデアと視点を最大限に活用したいと思い、会議やディスカッションの際には注意深くメンバーの発言を聞き、その意見や提案を尊重する姿勢を大切にしました。また、チームメンバーが意見を述べ終えるまで待つことで、誰もが自身の考えを十分に表現できるようにしました。
その結果、チームのメンバーと良好な関係を構築することができ、データ収集や分析、プレゼンテーションなどの準備を円滑に進められました。担当の教授からもチームでの研究の進め方・プロセスを評価していただきました。
入社後も自分の傾聴力を活かして、社内メンバーの意見や考えを取り入れながら、開発プロジェクトに専念したいと考えています。
ゼミ活動
ゼミ活動の例
私の強みは、立場が異なる人の真意を聞き出せる傾聴力です。
私は、所属ゼミのメンバーと地元企業の社員で、「◯◯共同研究プロジェクト」をゼミ活動としてスタートしました。
プロジェクト開始時、ゼミメンバーはアイデアを出し合ったり、積極的に発言したりすることに慣れておらず、課題を解決することに時間を要していました。一人ひとりに話を振り、こちらから質問をしながら話を聞き始めると、メンバーはこれまで言えなかったアイデアや、自分の思いを少しずつ話せるようになりました。
相手が本当は何を言いたいか、どうすれば思っていることを話してくれるのかを引き出す力が、ゼミ活動のなかで学べました。
相手の意見を聞き、まとめて伝えるということは、ゼミメンバー同士のコミュニケーションだけではなく、私と企業担当者とのやりとりでも活用でき、社会人の一員として役に立つスキルが身についたと実感しています。
部活・サークル
部活・サークルの例
私の強みは「傾聴力」であり、大学のバスケットサークルで培うことができました。
先輩から「来年こそライバルの大学との試合に勝ってほしい」と言われており、私はメンバーとその目標を達成するため練習に励んできました。
私はサークルのリーダーであり、「どうすれば試合で勝てるか」を日々考えていました。そのなかで、練習をするだけではなく、メンバーの声にも耳を傾けることが必要だと気づきました。
まず、ただ自分が意見を言うだけではなく「◯◯をしたいがどう思うか」と話を振り発言しやすい環境づくりを行いました。そして、意見を出してくれたメンバーには「なぜそう思ったのか」を聞くなどして、それまで以上に深い話し合いに導くことができました。また、これまでメンバーの意見に耳を傾けていなかったことに反省する機会にもなりました。
この経験から、チームでひとつの目標を達成するためには、傾聴力が必要だと学びました。入社後は、私の傾聴力を活かしプロジェクトをまとめるリーダーとして活躍したいと思います。
アルバイト
アルバイトの例
私は大学2年生のときから、居酒屋で接客のアルバイトをしています。アルバイトを始めた当初居酒屋はオープンしたばかりで、自分が接客に不慣れなこともあり、お客様やバイト仲間に迷惑をかけることもありました。
アルバイトのなかで、お客様の注文を誤ることが続き、短期間に数件クレームをいただいたことがありました。店の評判低下や食材ロス、会計のミスにもつながりかねないため、アルバイトメンバー5人と話し合いをし、どうすればミスが出ないかを話し合いをしました。
解決策は「注文内容を繰り返す」「メニュー名をできるだけ覚える」「わからないことはその場で聞く」「メニューの写真を指で指して確認する」といったことを徹底しました。メンバーがそれぞれやっていたことではありますが、話し合いの場を設けることで、メンバー全員が解決策を共有・実施できました。
アイデアを聞き出すこと、メンバーでコミュニケーションを取って共有することが、問題解決には欠かせないとアルバイトで学べました。傾聴力を用いた問題解決力は、御社の業務で活かせると考えています。
ボランティア活動
ボランティア活動の例
私の強みは、ボランティア活動で培った傾聴力です。
私の大学のボランティアサークルでは、定期的に地元の老人ホームに訪問し、レクリエーションを行っていました。手足を動かす、頭を使うなど、入所者のリフレッシュにつながる遊びを行っていました。
似たようなレクリエーションでは入所者の方も飽きてしまい、刺激にならないと考えました。入所者の方に直接、どのレクリエーションが好きか、どういう動きができるか・できないかを教えていただきながら、スタッフの方とともに新しいアイデアを考え、道具の作成などを行いました。
私が考えた「◯◯」という新しい遊びは入所者、スタッフともに評判だったことが非常に嬉しかったです。レクリエーションが苦手であまり参加しなかった入所者の方も、様子を覗いたり時折笑ったりと、以前より明るくなった姿が印象的でした。
ただ、レクリエーションを行うだけではなく、アイデアを生み出すためにはヒアリングが大切だとわかりました。目の前にあるものに満足せず、常に新しいものを作っていくためには、傾聴力が必要です。ボランティア活動で培った私の傾聴力を、御社の業務でも活かしたいです。
-
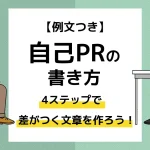
-
【例文つき】自己PRの書き方|4ステップで差がつく文章を作ろう!
自己PRでは、企業が求める人物像を把握したうえで「その強みを企業でどう活かせるか」まで伝えることが重要です。この記事では、自己PRの考え方と書き方を詳しく解説します。アピールポイント別の例文も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
続きを見る
よくある質問
傾聴力とは何ですか?
傾聴力とは、話す内容や様子から相手の感情や悩みを理解する能力を指します。「聞き上手」とは異なり、相手が見せていない心を読み取ることや、問題解決まで導ける能力をもっていることが特徴です。
傾聴力を自己PRや長所としてアピールするときのポイントはありますか?
自己PRや長所で傾聴力をアピールするときは、これらのポイントに注目しましょう。
・企業がどんな能力を求めているのかを確認する
・傾聴力を発揮したエピソードを伝える
・第三者からのフィードバックや評価を引用する
・傾聴力が応募先企業でどう活かせるかを説明する
・傾聴力をほかの言葉に言い換えできないかを検討する
各項目の詳細は「自己PRで傾聴力をアピールする場合のポイント」で解説しています。
傾聴力の言い換えは?
傾聴力と言い換える場合、これらの言葉を活用できます。
・調和力
・理解力
・洞察力
・問題解決力
「傾聴力」という言葉を、より自分の特徴に近い言葉と言い替えることで、自己PRをしやすくなる可能性があります。類語の詳細は「傾聴力をほかの言葉に言い換えできないかを検討する」で解説しています。
傾聴力を高めるトレーニング方法を教えてください
傾聴力を高める方法は、次のとおりです。
・相手の話を聞く姿勢・態度を意識する
・相手の話を聞く割合を増やす
・相手の反応を見ながら発言する
・相手のペースに合わせて会話する
・相手の話に肯定する
傾聴力は一朝一夕で身につくものではないため、日々の会話でこれらのことを意識しながら話してみてください。詳しくは「傾聴力を高めるトレーニング方法」で紹介しています。
傾聴力がある人の特徴は何ですか?
傾聴力が高い人には、次のような特徴があります。
・相手の話を遮らない
・相手にとって心地のよい相づちをする
・相手がしてほしい質問をする
身近に傾聴力が高いと思う人がいるときは、その人が話している様子や相づちを観察し、真似をしてみるのもよいかもしれません。詳しくは「傾聴力が高い人の特徴」で紹介しています。