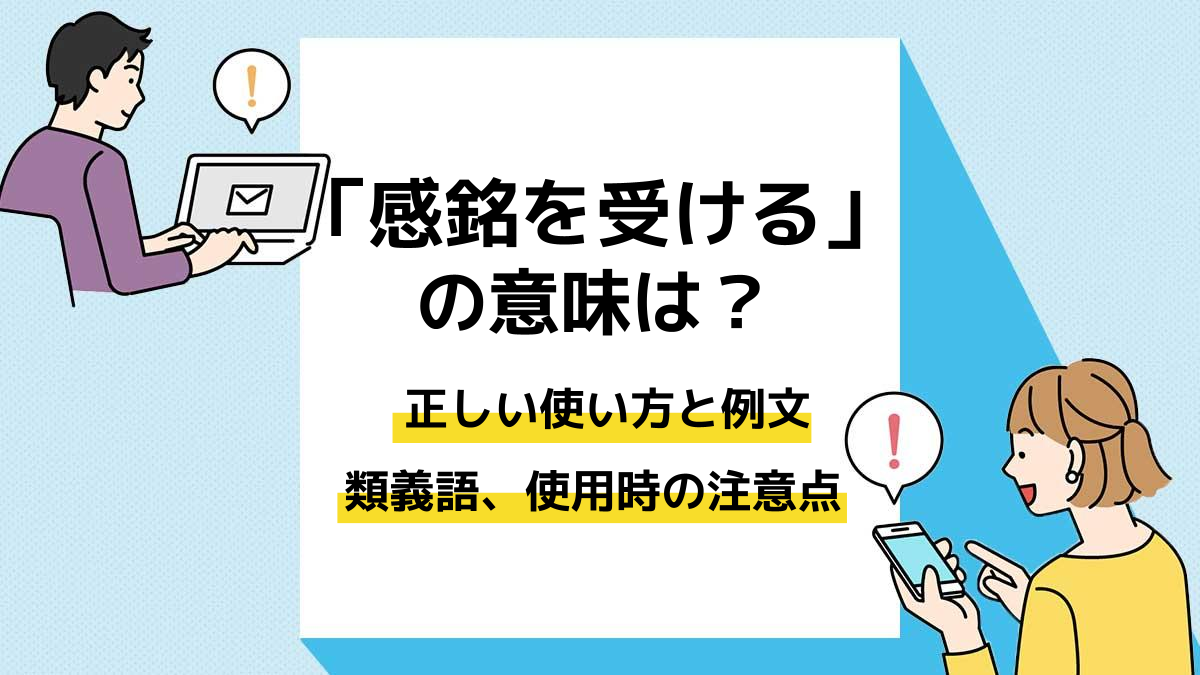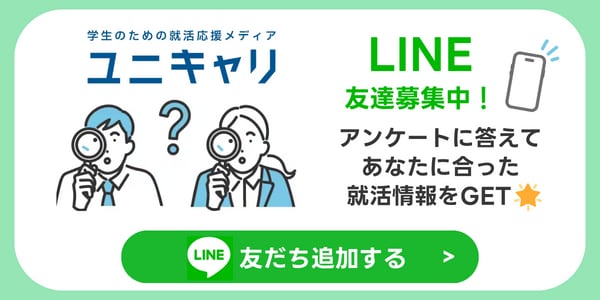「感銘を受ける」は、深い感動や印象が心に強く刻まれることを意味する表現です。ビジネスシーンや就活などのフォーマルなシーンで使われることの多い表現ですが、日常生活でも感動を伝える際に使うことができます。
この記事では、「感銘を受ける」の意味や使い方を例文とともにわかりやすく解説します。類義語や言い換え表現、英語表現も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事でわかること
- 感銘とは、深く感動して、その感情が心に強く刻まれて忘れないこと
- 志望動機で「感銘を受ける」を使うと、企業への敬意や影響の深さを強調できる
- 「何に感銘を受けたのか」を具体的に伝えることで説得力が増す
目次[表示]
「感銘を受ける」はどんな意味?
「感銘を受ける(かんめいをうける)」は、心に深く刻まれるような強い感動や影響を受けることを意味する表現です。単に驚いたり感動したりするだけでなく、そのできごとや体験が心に強く残り、価値観や考え方に影響を与える場面で使われます。
「感銘」はかつて「肝銘」と表記されることもありましたが、昨今では「感銘」と書くことが一般的です。
「感銘を受ける」は改まった会話や文章で用いられることが多く、やや堅い表現ですが、日常会話でもニュアンスによっては使うことができます。
感銘:深く感動し、その感情や印象が心に強く刻まれること
「感銘」とは、深く感動して、その感情が心に強く刻まれて忘れないことです。「感」は「感じること」、「銘」は「刻みつけること」の意味を持ちます。
感銘には、次のようなニュアンスが含まれます。
- 深い感動:表面的な感動ではなく、心の奥底に響くような感情
- 記憶に残る体験:長く心に刻まれ、忘れられない経験
- 価値観の変化:その体験が人生や考え方に影響を与える
例えば、誰かの行動に心を打たれたり、感動的な映画や本に出会ったりした際に「感銘を受ける」という表現が使われます。
「感銘を受ける」の正しい使い方と例文
「感銘を受ける」はおもに次の3つの場面に使われます。
それぞれの場面での正しい使い方を見ていきましょう。
ビジネスシーンやフォーマルな場面で使用する場合
「感銘を受ける」は、クライアントとのやりとりや営業などのビジネスシーン、スピーチ、公式の手紙などのフォーマルな場面でよく使われます。相手への敬意や深い感動を伝える際に適した表現です。
例文
- 御社の長年にわたる社会貢献活動に感銘を受けました。
- 貴社が長年続けてこられた活動の意義深さに、心より感銘を受けました
- 御社の◯◯プロジェクトにおける柔軟なご対応には深く感銘を受けました。
- 講演会での◯◯に関するご発言に深く感銘を受けました。
- この度のご講演を拝聴し、貴殿の経験に基づく貴重なお話に感銘を受けました。
就活・転職活動の面接や履歴書で使用する場合
面接や履歴書、ES(エントリーシート)で志望動機を伝える際に「感銘を受ける」を使うと、応募先の企業への敬意や、その影響の深さを強調できます。
ただし、「感銘を受ける」を使いすぎると信憑性が薄れてしまう場合があるため、特別な場面に絞って使うことがおすすめです。
面接の使用例
- 御社の掲げる「社会と共に成長する」という理念に深く感銘を受け、自分もその一員として活躍したいと考えました。
- 説明会での社員の方々のお話に感銘を受け、私も御社の一員として働きたいという思いを強くしました。
- 先日のインターンシップでは、社員の方々の姿勢に感銘を受け、御社で働くことが自身の成長に繋がると確信しました。
ES・履歴書での使用例
- 貴社の取り組む「未来を見据えた製品開発」に感銘を受け、そのなかで自分のスキルを活かしていきたいと思い、志望いたしました。
- 採用ページで拝見した社員インタビューに感銘を受け、御社が育成に力を入れている環境で成長したいと強く感じました。
- 貴社の「お客様第一主義」を掲げた姿勢に深く感銘を受け、これまでの経験を活かし、お客様に寄り添うサービスを提供したいと考えています。
-
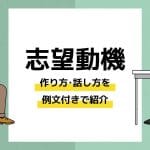
-
面接で伝える志望動機の作り方・話し方を例文付きで解説【新卒就活】
面接で志望動機を答えるときは、簡潔に伝えること、具体的なエピソードを盛り込むことが大切です。エントリーシートと同じエピソードでもよいですが、面接では深掘りして志望した理由を伝えましょう。この記事では、面接での志望動機の答え方の例文を交えて、伝え方のコツを紹介します。
続きを見る
日常会話のなかで使用する場合
「感銘を受ける」は、日常生活のなかでも特別なできごとや感動的な体験を語る際に使うことができます。
相手に感動の深さを伝える際に役立つ表現です。
例文
- 友人の誠実な態度に感銘を受け、私も見習いたいと思いました。
- その本を読んで感銘を受けて、考え方が少し変わった気がする。
- 昨日のライブ、アーティストの表現力に感銘を受けて涙が出そうになったよ。
- 忙しいなかでも家族を優先する姿に感銘を受け、自分ももっと家族を大切にしたいと思った。
- ドキュメンタリー映画を観て、現地の人々が困難に立ち向かう姿に深く感銘を受けた。
少しフォーマルなニュアンスを加えたい場面で適しており、日常会話では、「感動した」「心に響いた」などの表現のほうが自然な場合もあります。
「感銘を受ける」を使うときの注意点
ここでは、「感銘を受ける」を使う際に気をつけたい注意点を解説します。
ネガティブな対象や軽い感想には使わない
「感銘を受ける」は、敬意や感謝を込めて使う言葉であり、相手や対象を高く評価する文脈で使用するのが適切です。そのため、ネガティブな対象や軽い感想を伝える際には不向きです。
単なる「驚き」や「面白さ」を表す場面で使うと、違和感を与える可能性があります。ネガティブな対象や軽い感想を伝える際は、「感銘」以外の表現を使いましょう。
例文
- 失敗談を聞いて感銘を受けました。(敬意を欠く印象を与える可能性がある)
→失敗談を伺い、深く考えさせられました。 - 新しいスマートフォンの性能の高さに感銘を受けた。(一時的で軽い感想)
→新しいスマートフォンの性能の高さに感動した。
感銘を受けた対象を具体的に述べる
「感銘を受ける」は感情を深く伝える言葉なので、具体的な対象を明確にすることで説得力が増します。特に、面接などで志望動機を述べる際には、「何に感銘を受けたのか」を具体的に伝えることで、思いの深さが伝わりやすくなります。
例
とても感銘を受けました。(具体性が欠ける)
→彼の逆境に負けない姿勢に感銘を受けました。
日常会話よりフォーマルな場面で使う
「感銘を受ける」は堅めの表現であり、日常会話よりもビジネスシーンやフォーマルな場面でよく使われます。カジュアルな日常会話では、「感動した」や「胸を打たれた」といった表現のほうが自然な場合があります。
カジュアルな会話の例
昨日のテレビ番組に感銘を受けたよ。(やや堅すぎる)
→昨日のテレビ番組には感動したよ。

日常会話では、ニュアンスや相手によって使い分けることがおすすめです。
「感銘を受ける」の類義語・言い換え
「感銘を受ける」の類義語や言い換え表現を、文脈や状況に応じて適切に使い分けることで、感情や印象をより的確に伝えることができます。
「感銘」は、深い感動や大きな影響を伴う場面に適しているため、ほかの表現と区別して使うことがおすすめです。
| 言い換え表現 | 意味・例文 |
| 感動する | 心が動かされる 例文:その演奏に感動しました。 |
| 感服する | 相手の行動や能力に敬意を持って感心する 例文:彼の粘り強い努力に感服しました。 |
| 胸を打たれる | 心に強く響く 例文:彼の真摯な言葉に胸を打たれました。 |
| 啓発される | 新しい気づきを得る 例文:ご指導を通じて、新たな視点に啓発されました。 |
| 感慨深い | 過去のできごとや状況を振り返り、深く感動するさま 例文:努力したことが形になり、感慨深いです。 |
| 驚嘆する | 素晴らしさや意外性に驚き、感心する 例文:その技術力の高さに驚嘆しました。 |
| 心を動かされる | 強い感情や共感を抱く 例文:映画を観て心を動かされました。 |
| 心に響く | 言葉や行動が心の深い部分に届く 例文:先生のお話は、どれも心に響きました。 |
| 心を揺さぶられる | 感情が強く動かされる 例文:今朝のニュースに心を揺さぶられました。 |
| 共感する | 他人の気持ちや意見に同じ気持ちを抱く 例文:彼女の考え方に深く共感しました。 |
| 共鳴する | 自分の考えや気持ちと一致し、強く共感する 例文:彼の話に深く共鳴しました。 |
| 衝撃を受ける | 予想外のできごとに驚き、強い感情を抱く 例文:突然の発表に衝撃を受けました。 |
| 心を打たれる | 強く感動する 例文:子どもたちの一生懸命な姿に心を打たれました。 |
| 心が震える | 強い感動や感情の高まりを感じる 例文:オーケストラの演奏に心が震えました。 |
| 深く刻まれる | 忘れられない強い印象を心に残す 例文:彼の言葉は私の心に深く刻まれました。 |
| 圧倒される | 味:非常に感動し、圧倒的な印象を受ける 例文:彼の技術力は素晴らしく、圧倒されました。 |
「感銘を受ける」の対義語
「感銘を受ける」に直接対応する明確な対義語はありませんが、感動や深い印象を受けることの反対の状態を表す言葉はあります。
例えば、感情が動かない、心に響かない状態を表す言葉としては、次のような表現があります。
- 無関心:特に興味や関心を抱かないこと
- 無感動:心が動かされることがない
- 無反応:何も感じない、反応しないこと
- 記憶に残らない:特に印象に残らず忘れてしまうこと
- 印象が薄い:特に強い印象を与えないこと
感銘を受けることを期待していたにもかかわらず、不快感や否定的な印象を抱いたことを示す表現は次のとおりです。
- 失望する:期待していたものが裏切られたときに感じる感情
- 落胆する:期待が外れてがっかりすること
- 興ざめする:楽しみや感動が一気に冷めること
- 嫌悪感を抱く:強い不快感や嫌な感情を持つこと
- 反感を覚える:相手の行動や言葉に反発心を持つこと
- 冷淡:冷たい態度や無関心を表すこと
「感銘を受ける」の英語表現
「感銘を受ける」を英語で表現する際には、次の3つのフレーズがよく使われます。
それぞれの意味や使い方、例文を確認していきましょう。
be impressed by 〜
「be impressed by 〜」は、「~に感銘を受ける」「~に強い印象を受ける」という意味を持ちます。フォーマルな場面やビジネスシーンでも幅広く使える表現です。
例文
- I was deeply impressed by his dedication to the project.
(彼のプロジェクトへの献身に深く感銘を受けました。) - She was impressed by the artwork at the gallery.
(彼女はギャラリーで見た芸術作品に感銘を受けました。)
be moved by 〜
「be moved by 〜」は、「~に感銘を受ける」だけでなく、「感動する」というニュアンスを含みます。特に感情的な影響を強調したいときに適した表現です。
具体例
- I was strongly moved by the ending to the movie.
(映画の終わりを見て、感銘を受けました/感動しました。) - We were deeply moved by their heartfelt performance.
(私たちは彼らの心のこもったパフォーマンスに深く感銘を受けました。)
be inspired by〜
「be inspired by 〜」は、「~に深く触発される」「~に感銘を受ける」という意味で、特に相手の行動や価値観から刺激を受けた場合に使います。
具体例
- She was inspired by her teacher’s passion for education.
(彼女は先生の教育に対する情熱に感銘を受けました。) - Many people are inspired by stories of overcoming adversity.
(多くの人々が逆境を克服する物語に感銘を受けます。)
よくある質問
「感銘を受ける」の意味は?
「感銘を受ける」とは、深い感動や印象が心に強く刻まれることを意味します。一時的な感動ではなく、そのできごとや言葉が長く記憶に残り、価値観や考え方に影響を与えるような場面で使われる表現です。
「感銘を受ける」の軽い言い方を教えてください。
「感銘を受ける」の軽い言い方として、「感動した」「心に響いた」「印象に残った」などがあります。これらは日常会話やカジュアルな場面で使いやすい表現です。
「感銘を受ける」を目上の人に使用できますか?
目上の人にも使用できます。「感銘を受ける」は、敬意を込めた深い感動を伝える言葉として適切な表現です。具体的な内容を添えて、「◯◯に感銘を受けました」と述べると、より真摯な印象を与えます。
「感銘を受ける」の敬語表現は?
「感銘を受ける」の丁寧な表現として、「深く感銘を受けました」や「心より感銘を覚えました」などがあります。特にビジネスやフォーマルな場面では、丁寧語や謙譲語を用いると適切な敬語表現になります。
「感銘をする」は間違いですか?
「感銘をする」ではなく「感銘を受ける」が正しい表現です。「感銘」は外部からの影響で心に刻まれる感動を指すため、「受ける」と組み合わせて使うことが適切です。「感銘を覚える」と表現することもあります。